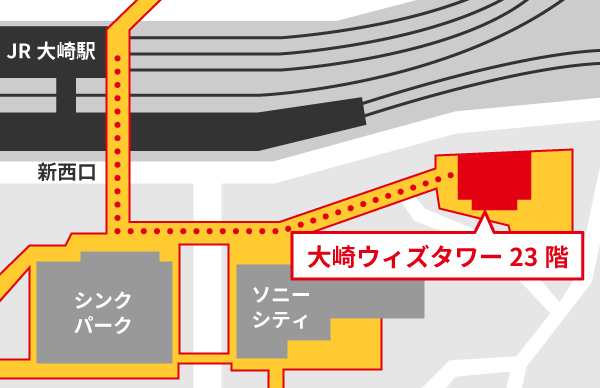個人事業主や企業などが業務用として車を購入する場合、固定資産扱いとなります。固定資産の場合、減価償却の形で経費を計上していく必要があります。
減価償却の期間は法律で定められていて、ルールに従い償却することが大切です。しかし、所有する車の減価償却が完了していない方の中には、車の買い替えを検討している方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、減価償却中の車の買い替え方法について詳しく解説します。あわせて、減価償却の仕訳のポイントや買い替える際の注意点などについてもまとめました。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
少しでも損をしたくない方は下記の「無料査定はこちら」から無料査定をしてみてください。
この記事でわかること
- ・減価償却中に車を買い換える方法
- ・車を売却する場合の減価償却方法
- ・車の売却時の仕訳のポイント
| かんたん30秒! 愛車の高価買取なら【カーセブン】 | |
愛車を高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です! \簡単30秒/ |
減価償却中でも車を買い替えることはできる?
車の法定耐用年数は、新車の場合は普通車で6年、軽自動車で4年と定められています。しかし、減価償却が完了していない段階で車を買い替えたい場合、ルールに従い対応すれば買い替えることは可能です。
減価償却の場合、各資産別に設定されている耐用年数をベースに、分割して毎年経費として計上する形となります。また、減価償却には、毎年一定の金額で行う定額法と、毎年一定の率で行う定率法の2種類があります。
いずれの方法においても、減価償却が完了していない状態で売却は可能です。しかし、売却益(益金)か売却損(損金)かを決定する必要があるので覚えておくと良いでしょう。
減価償却とは?
減価償却中の車を売却するためには、減価償却について理解する必要があります。ここでは、減価償却と耐用年数について詳しく解説します。減価償却は法律に従った対応が求められるため、ここで解説する内容を正しく理解することが大切です。
減価償却とは?
減価償却とは、主に企業の会計において購入費用の認識と計算する方法のことです。長期間にわたって使用する固定資産を取得する際にかかった支出を、対象の資産が使用できる期間で費用配分する手続きとなります。
日本においては、各期に計上されている費用を減価償却費と呼びます。全体の支出額を各年度の費用で配分することで、各年度で見ると損益とキャッシュフローとで差が生じることになるのです。
減価償却の場合、事前に決定した償却法と耐用年数を用いて、資産毎の年間の償却額を算出します。ただし、会計期間に取得した資産については、年間償却額を月割計算した額が決まります。
耐用年数とは?
耐用年数とは、対象となる資産を使用できる期間のことです。減価償却資産は、使用すればするほど物理的に損耗し、価値が下がります。
法定耐用年数については、資産の耐久性などに応じて明確な決まりがあるため、自分で勝手に設定することはできません。車の場合は、普通乗用車が6年、軽自動車が4年となっています。
中古車の場合は、以下の2つのパターンで耐用年数を算出方法が用意されています。
| 状態 | 耐用年数 |
| 耐用年数の全てが経過している場合 | 耐用年数の20%に当たる年数を耐用年数とする |
| 耐用年数の一部が経過している場合 | 耐用年数の経過分の年数を引いた年数に、経過年数の20%にあたる年数を加えたものを耐用年数とする |
上記はあくまでも一般的な算出方法であり、一般用や事業用など用途や構造により耐用年数が異なります。保有している車の耐用年数を確認したい場合は、国税庁のホームページで確認すると良いでしょう。
減価償却の2つの方法
減価償却する際には、定額法と定率法の2つの方法があります。計算方法が異なるだけでなく、それぞれにメリット・デメリットがあるので、最適な方法を選ぶことが大切です。ここでは、減価償却する方法となる定額法と定率法について詳しく解説します。
定額法と定率法
定額法と定率法とは、減価償却する際に耐用年数の中で計上する売却額をどのように算出するのかの方法です。それぞれの方法の詳細は、以下のとおりです。
定額法とは?
定額法とは、毎年の償却額が均等となるように計算する方法です。定額法を用いた場合の減価償却費の計算式は、以下となります。
定額法の減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
普通車の場合、6年が耐用年数となるため定額法償却率は0.167(耐用年数6年→1÷6=0.166…を端数処理して0.167)となります。減価償却費を毎年同じ金額を償却すると、単純計算では最終的に0円となってしまいます。
ただし、帳簿上では0円でも実際には固定資産を保有している関係上、耐用年数の最終年には期末(最終年)は備忘価額として1円を残す計上する形がとられるのです。
定率法とは?
定率法とは、減価償却費が一定の割合により減少する方法のことです。減価償却費の計上金額については、最初の段階が大きくて年数が経過すると徐々に小さくなる特徴があります。
定率法の計算式は、以下のとおりです。
定率法の減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
計算するうえで注意したいのは、上記の計算において償却保証額を満たさない場合に、その年分以降については改定取得価額に改定償却率をかけて計算しなければならない点です。耐用年数の最終年については、定額法と同様に減価帳簿価額を1円残して計上されます。
定額法と定率法どちらを使用すればよい?
定額法と定率法は、似て非なるものであり、どちらを選択するのかは自由です。定率法を利用する場合、購入した初年度に多くの減価償却費を計上可能であり、購入直後の利益を下げられます。
定額法を選択すると、毎年同じ額を費用に計上できるため、資金計画を立てやすい特徴があります。以上の特徴を加味して、どちらの方法を採用するのかを決めましょう。
なお、途中から定額法から定率法に変更することも可能です。変更する場合は変更した年の1月1日における未償却残額と、その減価償却資産に関連する改定取得価額またはその減価償却資産の取得価額を基礎として計算します。
その減価償却資産について、定められた耐用年数による償却率、改定償却率または保証率により計算しなければなりません。
減価償却中の仕訳
ここでは、減価償却中に車の売却を行った場合の仕訳方法を紹介します。個人と法人それぞれの仕訳方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
減価償却中の個人の仕訳
個人事業主が車を売却する場合、個人名義から買取業者に譲渡した扱いとなります。そこで、総合課税所得の譲渡所得という形で計上することになります。
そのため、勘定科目については事業主借や事業主貸で仕訳するのが一般的です。たとえば、200万円で普通自動車を新車で購入して、3年間乗ったあとに110万円で売却したとしましょう。
このケースでは、耐用年数がまだすべて経過していないので、購入時点での金額となる225万円をすべて経費にできません。普通自動車の耐用年数となる6年で割り、毎年375,000円ずつ計上する必要があります。
また、3年間利用しているため、購入価格より1,125,000円が減価償却費として差し引き、期首帳簿価額の形で貸方に車両運搬具として同額の1,125,000円を記入しましょう。さらに、購入時に負担したリサイクル預託金の18,000円についても、預託金として貸方に記入しましょう。
そして、売却した110万円は現預金の科目で借方に組み込み、売却益となる事業主貸の科目で借方に記入します。ここまでの流れをまとめると、以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 1,100,000 | 車両運搬費 | 1,125,000 |
| 事業主貸 | 43,000 | 預託金 | 18,000円 |
| 合計 | 1,143,000 | 合計 | 1,143,000 |
減価償却中の法人の仕訳
法人で車を売却した場合の売却損益は、事業の支出や収入の形となります。そのため、固定資産売却損益として仕訳しましょう。同じく、220万円で新車の普通車を購入し、3年後に110万円で売却した場合の仕訳結果は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 1,100,000 | 車両運搬費 | 1,125,000 |
| 固定資産売却損 | 43,000 | 預託金 | 18,000 |
| 合計 | 1,143,000 | 合計 | 1,143,000 |
個人のものとは違いは、事業主貸となっていた箇所が固定資産売却損となった点のみです。上記は売却損が発生した場合の例ですが、売却して売却益が発生した場合はまた仕訳が変化します。
220万円で新車の普通車を購入して、1年後に190万円で売却した場合の仕訳結果がこちらです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 1,900,000 | 車両運搬費 | 1,825,000 |
| 預託金 | 18,000 | ||
| 固定資産売却益 | 19,825 | ||
| 合計 | 1,900,000 | 合計 | 1,900,000 |
これより、19,825円が売却益となったことがわかります。車を売却して発生した損益は、法人の場合は固定資産売却損、または固定資産売却益を勘定科目としましょう。
減価償却中に下取りもしてもらう場合の仕訳
減価償却中に、買取ではなく下取りしてもらうケースもあります。下取りとは、ディーラーなどで新車を購入することを前提として、古い車を買い取ってもらうことです。
車の売却と購入を一緒に行い、また売却金額をそのまま新車購入価格に充てるため仕訳が複雑となります。仕訳を解説するための前提条件を、以下としましょう。
・新車購入価格(本体価格とオプションの合計):2,800,000円
・リサイクル預託金:18,000円(資産管理料金380円含む)
・環境性能割、重量税、法定費用の合計:60,000円
・自賠責保険、任意保険の合計:50,000円
・代行費用などの諸経費:80,000円
環境性能割や重量税は租税公課となり、代行費用などの諸経費は支払手数料として仕訳する必要があります。また、リサイクル預託金の資産管理料金については、費用として計上する必要があり支払手数料に仕訳する形を取ります。上記の内容をまとめた結果が、以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 車両運搬具 | 2,800,000 | 現預金 | 3,008,000 |
| 支払手数料 | 80,380 | ||
| 保険料 | 50,000 | ||
| 租税公課 | 60,000 | ||
| 預託金 | 17,620 |
下取りに関する仕訳については、基本的には買取と同じ形で仕分けていきます。減価償却累計分を差し引いて、下取り価格より下回るか上回るかで固定資産売却損益を計算しましょう。
220万円で新車の普通車を購入して、1年後に190万円で売却した場合の仕訳結果は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 車両運搬具 | 2,800,000 | 現預金 | 1,145,175 |
| 支払手数料 | 80,380 | 車両運搬費 | 1,825,000 |
| 保険料 | 50,000 | 預託金 | 18,000 |
| 租税公課 | 60,000 | 固定資産売却益 | 19,825 |
| 預託金 | 17,620 | ||
| 合計 | 3,008,000 | 合計 | 3,008,000 |
一気に計算しようとすると分かりにくくなりますが、新車購入と売却を分けて仕訳すれば比較的簡単に仕訳することができるでしょう。
リース車の場合の仕訳
車を購入する場合、自己保有ではなくリース契約したうえで保有する場合があります。リース車の場合はレンタカーとは異なり通常の購入と同様に注文して製造、新車登録できます。
見た目は購入した車と一切変わらないものの、車検証上の所有者欄はリース会社で、使用者欄は利用者という形となるのです。利用者はリース会社に対して、毎月一定額を支払うことにより車を保有することができます。
リース車を利用する際に支払うリース料は、費用として計上できます。車を購入する場合は固定資産として計上する一方で、リース車の場合は流動費となり原則としてリース料は期間対応で費用計上(ファイナンス・オペレーティングの区分に留意)できる関係上節税効果が高いでしょう。
さらに、リースの場合は税金や車検といった費用がすべてリース料に含まれており、減価償却も必要ありません。
ローンが残っている場合の仕訳
車を購入する際に、ローンを組む場合があるでしょう。ローンを組んで車を購入した場合の仕訳は、元金部分は経費に計上できません。頭金を負担して購入したケースでは、納車されたタイミングでの仕訳で頭金を仮払金の科目で貸方に、ローンの元金については長期未払金として貸方に記入しましょう。
また、ローン手数料については長期前払費用の科目で借方に記入する必要があります。これらの内容ををまとめると、以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 車両運搬具 | 2,800,000 | 仮払金 | 1,500,000 |
| 支払手数料 | 80,380 | 長期未払金 | 1,673,000 |
| 保険料 | 50,000 | ||
| 租税公課 | 60,000 | ||
| 預託金 | 17,620 | ||
| 長期前払費用 | 165,000 | ||
| 合計 | 3,173,000 | 合計 | 3,173,000 |
なお、ローン手数料の部分については経費として計上することが可能です。そのため、毎月のローンを返済する際の仕訳においては、支払利息として借方に記入しましょう。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 長期未払金 | 31,277 | 現預金 | 31,277 |
| 支払利息 | 2,660 | 長期前払費用 | 2,660 |
| 合計 | 33,937 | 合計 | 33,937 |
以上のように、ローン手数料は確実に経費として計上し、節税に努めると良いでしょう。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
少しでも損をしたくない方は下記の「無料査定はこちら」から無料査定をしてみてください。
| かんたん30秒! 愛車の高価買取なら【カーセブン】 | |
愛車を高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です! \簡単30秒/ |
車の売却時の仕訳のポイント
車を売却する際に、仕訳するためのポイントとして以下のような点があります。
・直接法と間接法がある
・税込経理/税抜経理のいずれも可(方式は期首から継続適用)
・売却益と売却損の違い
上記に挙げた各ポイントについて、詳しく解説します。
直接法と間接法がある
車を売却する場合、減価償却累計額を差し引いて帳簿価額としなければなりません。固定資産の帳簿価額(取得原価−減価償却累計額)で表示する方法(直接法)のことを直接法と呼びます。
一方、減価償却費用を差し引くことなく別途減価償却累計額という形で記録する方法のことを間接法と呼びます。
それぞれにメリット・デメリットがあり、直接法の場合は固定資産の金額が貸借対照表の資産の科目と一致するのがメリットです。ただし、金額が年々減少するため取得原価が分からなくなってしまうのがデメリットとして挙げられます。
間接法の場合、固定資産科目の金額が変わらず減価償却の累計額が増加するため、取得原価を残すことが可能です。ただし、減価償却累計を減算しないと資産が分かりにくくなるデメリットもあるため、最適な方法を採用しましょう。
税込経理/税抜経理のいずれも可(方式は期首から継続適用)
仕訳を行う場合、税込なのか税抜にするのかについては、特に定められたものはなく、どちらを採用しても問題ありません。ただし、課税事業者であるケースでは、消費税を納付しなければならず、還付を受けるケースもあるため、可能な限り消費税の額を分けて処理するのが無難でしょう。
車を売却した場合に税込を採用するケースでは、車の売却額をそのまま税込で記入すればよいので余計な手間がかかりません。車の売却を税抜で計上する場合は、車両運搬具の科目で貸方に税抜の金額を、消費税については仮付消費税の科目で別途貸方に記録するようにしましょう。
売却益と売却損の違い
車を売却した場合、高く売れたと感じる場合と低く売れて損したと感じる場合があります。これは直感的に感じるものですが、経理上では売却益と売却損という形で区別されます。
売却益とは、利益が発生したことを意味し、車を売却した額が固定資産から減価償却累計を引いて算出できる帳簿価額を上回った場合のことです。一方、売却損とは売却額が帳簿価額を下回り損実が生じたことを意味します。
個人事業主が仕訳する場合、売却益は勘定科目で事業主借を、売却損は事業主貸として仕訳します。法人では、売却益は固定資産売却益で、売却損は固定資産売却損として仕訳しましょう。
減価償却中に車を売却する時の注意点
減価償却中に車を売却したい場合、注意すべきポイントとして以下のようなことが挙げられます。
・リサイクル預託金の仕訳も忘れないようにする
・わからないことがあれば税理士に相談する
・自動車税を納付する
・自動車納税証明書を用意する
・売却時は還付なし(廃車時のみ月割で還付)
各ポイントについて、詳しく解説します。
リサイクル預託金の仕訳も忘れないようにする
車を売却した場合、仕訳の中でリサイクル預託金の金額が必須となります。リサイクル預託金とは、将来的に車の解体が必要になった際の廃棄費用を、前払いしておく意味で負担する費用のことです。
リサイクル預託金は、車の解体や廃車に関連する業者が、適正に業務を行うために用いられています。リサイクル預託金は、普通自動車の場合は10,000円から18,000円、軽自動車は7,000円から16,000円程度です。
リサイクル預託金の内訳としては、資産管理料とそれ以外の費用という形で分類されます。資産管理料は費用として計上する一方で、それ以外は資産計上するようにしましょう。
また、車を売却した場合は相手方からリサイクル料金を受け取る必要がありますが、非課税取引となる関係上で車本体の売却額と別の勘定科目に仕訳けなければなりません。
わからないことがあれば税理士に相談する
仕訳などについては、専門的な知識が必要な項目も多数あります。特に、どのような科目でどの項目を仕訳すれば良いかを間違えると、修正申告が必要なため気を付けましょう。
少しでも経理上でわからないことがあれば、税理士に相談することをおすすめします。また、税金関係でも分からないことが発生する場合も多いため、相談できる税理士がいれば間違いなく手続きが進められるでしょう。
自動車税を納付する
車の売却を行う際には、自動車税は納税していなければなりません。自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している方に対して課税される税金です。
自動車税は、大半の自治体では5月末日までに納めなければなりません。自動車税が未納状態であると車を売却できないため、未払い状態の場合は早急に納付しましょう。
自動車税の納付書については、4月下旬から5月上旬頃に郵送されます。紛失してしまった場合は再発行してもらえるため、税事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
自動車納税証明書を用意する
車を売却する際に、名義変更する必要があります。車の名義変更手続きを行う場合、自動車税納税証明書が必要です。
自動車税納税証明書は、自動車税を納税したことを証明する書類で、受領印が押されます。自動車税の納付書に同封されていますが、紛失してしまう場合が多い書類でもあります。
紛失した場合は、早急に再発行手続きを行うことが大切です。再発行は通常は税事務所で行ってもらえますが、自治体によっては郵送で再発行対応しているケースもあります。
売却時は還付なし(廃車時のみ月割で還付)
自動車税や自動車重量税については、収めたものを売却した時点で還付を受けることはできません。自動車税や自動車重量税の還付制度自体は存在するものの、あくまでも車を廃車にした場合にのみに適用されます。
この場合、車の売却は譲渡という扱いになるため、還付されることはありません。税金の還付は受けられないものの、中古車買取業者などでは買取価格に上乗せしてくれるケースもあります。
査定時に金額が上乗せされているかについて、よく確認することをおすすめします。
減価償却のために車は買い替えるべき?
減価償却では、実際の費用を発生せずとも経費になるため、減価償却が計上できた方が節税を図ることができます。ただし、耐用年数があるため普通車の新車であれば、6年後には減価償却が終了し帳簿価額は1円にとなってしまいます。
減価償却が終了したから車を買い替えないというケースも多いですが、減価償却するために車を買い換えると判断する方もいます。ただし、後者の場合は車を購入すると手元のキャッシュを減らすことになるのです。
減価償却のために車を買い替えるよりも、税金を支払い続けた方がお金を残せるため、税金のために車を買い替えるということはおすすめしません。
まとめ
車を売却する場合、減価償却中でも売却を進めることは可能です。ただし、売却時の仕訳においては耐用年数から適切に減価償却する必要があります。
また、リサイクル預託金なども適切に計上する必要があります。仕訳を行ううえで不安に感じることがあれば、税理士に相談するなど適切に対応し、漏れなく仕訳することが重要です。
車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
少しでも損をしたくない方は下記の「無料査定はこちら」から無料査定をしてみてください。
| かんたん30秒! 愛車の高価買取なら【カーセブン】 | |
愛車を高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です! \簡単30秒/ |
もう乗らない…価値が下がる前が売り時
その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!