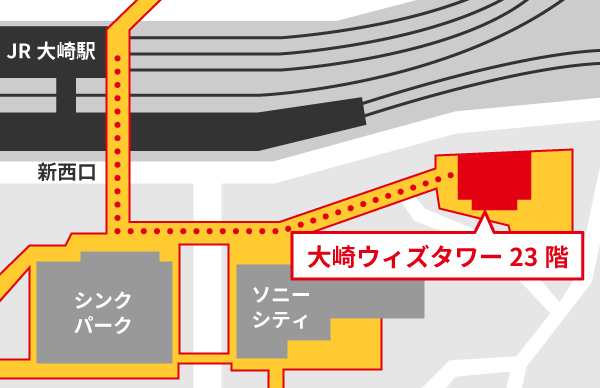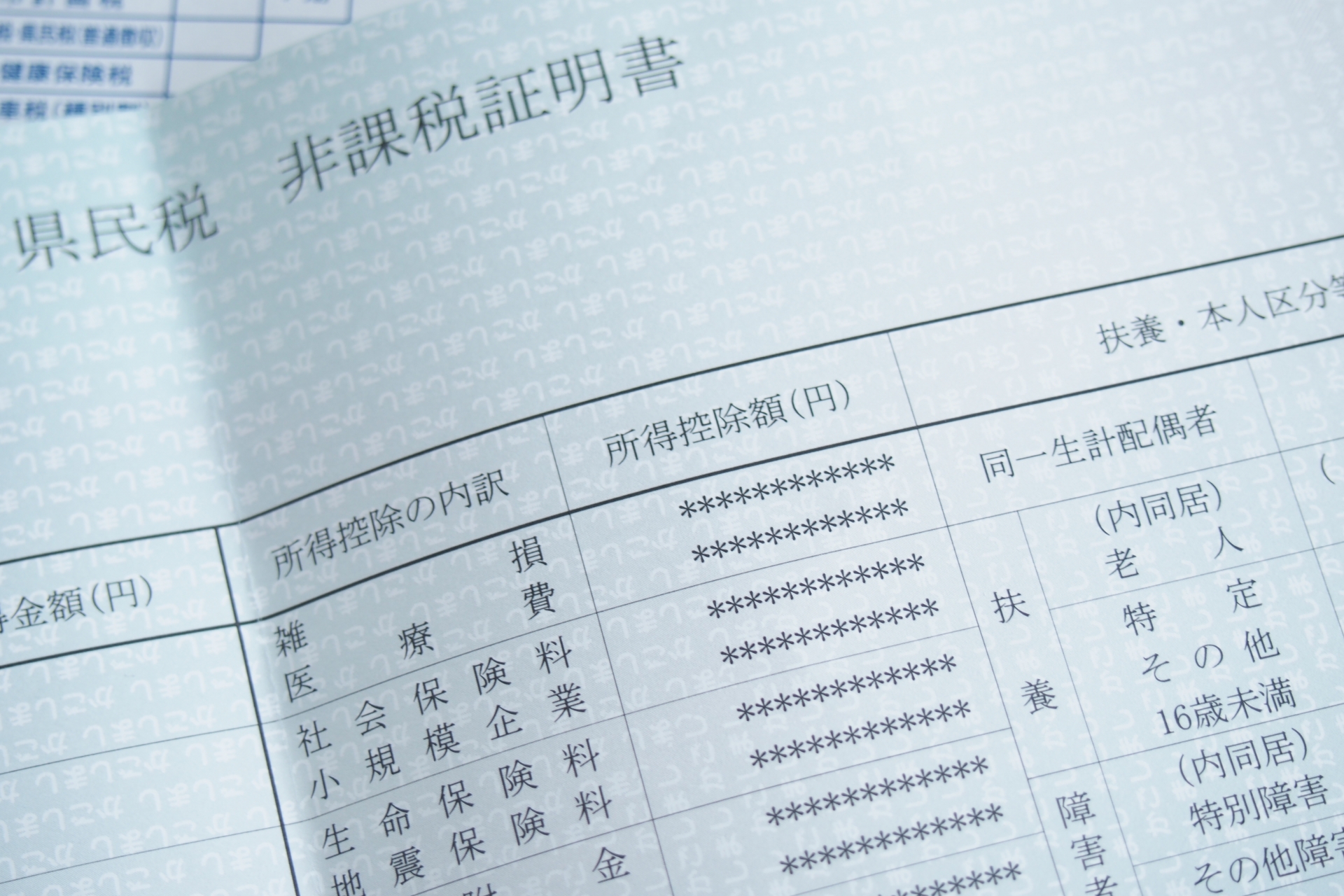
車検で納税証明書の提出が必要なのか、疑問を感じている方いませんか。納税証明書は、自動車税を支払ったことを証明する書類のことです。
そこでこの記事では、車検で納税証明書の提出が必要になるのかや納税証明書の提出を省略できる方法などを解説します。記事内では、納税証明書を再発行する方法についても合わせて紹介しています。気になる方は、ぜひ参考にしてください。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
少しでも損をしたくない方は下記の「無料査定はこちら」から無料査定をしてみてください。
この記事でわかること
- ・納税証明書の特徴
- ・納税証明書の再発行方法
- ・納税証明書を省略できる条件
| かんたん30秒! 愛車の高価買取なら【カーセブン】 | |
愛車を高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です! \簡単30秒/ |
目次
納税証明書とは?

納税証明書とは、一言で解説すると「地方自治体に地方税を納めたことを証明する書類」のことを意味します。2019年10月1日施行の税制改正により、普通自動車と軽自動車によって、納税証明書の正式名称が変更されました。
自動車税は、毎年4月1日時点で所有者に支払い請求書(納税通知書)が届きます。納税請求書は、お近くのコンビニや市役所などで支払い対応が可能です。
支払い後、請求書に領収日付印が押され、押印された書類が納税証明書となります。
普通自動車の税額
普通自動車の税額を、以下の表にわかりやすくまとめました。
| 排気量 | 2019年9月30日以前に登録された新車 | 2019年10月1日以降に登録された新車 | 新車として登録されて13年以上経過している場合 |
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 39,600円 |
| 1,001cc〜1,500cc | 34,500円 | 30,500円 | 39,600円 |
| 1,501cc〜2,000cc | 39,500円 | 36,000円 | 45,400円 |
| 2,001cc〜2,500cc | 45,000円 | 43,500円 | 51,700円 |
| 2,501cc〜3,000cc | 51,000円 | 50,000円 | 58,600円 |
| 3,001cc〜3,500cc | 58,000円 | 57,000円 | 66,700円 |
| 3,501cc〜4,000cc | 66,500円 | 65,500円 | 76,400円 |
| 4,001cc〜4,500cc | 76,500円 | 75,500円 | 87,900円 |
| 4,501cc〜6,000cc | 88,000円 | 87,000円 | 101,200円 |
| 6,001cc〜 | 111,000円 | 110,000円 | 127,600円 |
普通自動車の自動車税額は、車種ごとの排気量によって負担する金額が異なります。一般的に排気量が大きくなるほど、毎年負担する自動車税が高くなる仕組みです。
ただし、新車で購入した車によって、減税対策の対象車種に該当している可能性があります。そのため、まずは一度確認してみましょう。
軽自動車の税額
軽自動車の自動車税額を、以下の表にわかりやすくまとめました。
| 排気量 | 2019年9月30日以前に登録された新車 | 2019年10月1日以降に登録された新車 | 新車として登録されて13年以上経過している場合 |
| 660cc | 10,800円 | 10,800円 | 12,420円 |
軽自動車の場合、排気量は660ccで統一されているため、排気量ごとに自動車税額が異なることはありません。ただし、初度登録から13年以上経過している軽自動車の場合、自動車税額が15%〜20%ほど高くなるため注意しましょう。
納税証明書が必要になる状況

納税証明書が必要になる状況を4つまとめました。
・車検のとき
・車の売却のとき
・引っ越しのとき
・車の所有権が解除のとき
納税証明書が必要になる状況について、それぞれ詳しく解説します。
車検のとき
車の継続車検を行う際、自動車税を支払っていることを証明するために、納税証明書が必要になります。
ただし、登録車(普通自動車)の場合、2015年4月からオンライン上で納税情報を確認できるシステム「JNKS(自動車税納付確認システム)」が導入されているため、納税証明書の提示が省略されました。
軽自動車も「軽JNKS」の導入が徐々に進んでおり、2023年1月からは軽自動車の車検実施時に納税証明書の提示が原則不要になっています。車検を実施する際には、基本的に自動車税を滞納している状態では実施できません。
そのため、車検を受ける前までに、納税証明書の支払いを済ませておくように意識しましょう。
車の売却のとき
愛車を売却する際にも、納税証明書が必要です。なぜなら、前オーナーが自動車税を納付したことを事前確認するためです。自動車税の納付を事前確認していなければ、万が一、未納な場合に大きなトラブルに発展する可能性が考えられるでしょう。
引っ越しのとき

引越しなどで居住地が変更されたときや、新居住地で自動車税を納税前に車検を受けるときには、納税証明書が必要になります。
引越し後、すぐに車検を受ける予定がある人や車検期日が近づいている方は、事前に引越し前の自動車税納税証明書を処分せずに保管しておくことをおすすめします。
車の所有権が解除のとき
車の所有権を解除する際には、納税証明書の提出が必要になります。所有権解除手続きは、マイカーローン完済時に、車検証の所有者情報をディーラーやローン会社から変更する手続きです。
所有権解除の手続きを行う際には、ディーラーやローン会社に印鑑証明書や納税証明書、車検証の原本を郵送する必要があります。ディーラーやローン会社に納税証明書を郵送する際には、納税証明書の原本ではなく、書類のコピーでも問題ありません。
車検のときに納税証明書の提出を省略できる条件

車検のときに、納税証明書の提出を省略できる条件は3つあります。
・車検が継続検査の場合
・自動車税を滞納していない場合
・納税から2~4週間経っている場合
それぞれの条件を詳しく解説します。
車検が継続検査の場合
車検が継続検査の場合、納税証明書の提出が省略されます。現在、普通自動車と軽自動車のどちらも、オンライン上で納税情報を確認できるシステム「JNKS(自動車税納付確認システムの採用により、納税証明書の提出が省略されました。
ただし、車検時に納税証明書の提出が省略できる大前提は、車検前に自動車税を納付していることが絶対条件です。車検時までに自動車税を納付していなければ、継続車検を実施することができません。
自動車税を滞納していない場合
自動車税を滞納していない場合、納税証明書の提出が省略されます。自動車税の納税証明書は、あくまで自動車税の支払いを証明する書類です。
毎年、5月頃に車の所有者に届く納税額を支払っていれば、データー上で支払い状況を管理しているため、書類を保管する必要はありません。
納税から2~4週間経っている場合
納税から2〜4週間経過している場合、車検のときに納税証明書の提出を省略できます。現在、納税証明書の支払い状況は、国土交通省陸運局と都道府県事務所がオンライン上で確認できるようになりました。
ただし、自動二輪車の場合には、従来どおり自動車納税証明書の提出が必要になるため注意しましょう。
軽自動車も車検での納税証明書の提出が省略可能になった

車検を受ける際に「納税証明書の持参が必要」と認識している方も多いでしょう。以前までは、車検時に自動車税が確実に納付されているのかを確認するために、納税証明書の提出が絶対条件の業者が多くありました。
しかし、近年、納付確認の電子化により、オンライン上で納税確認を行えるシステムが普通車に限らず、軽自動車にも採用されています。一部納付確認システムが採用されていない地域も中にはあります。
車検を実施する業者に納税証明書が必要といわれることを想定して、納税証明書は車の中に保管しておくことをおすすめします。
自動車税種別割の納付確認が電子化

平成27年4月より、車検時に運輸支局・自動車検査登録事務所で行える自動車税種別割の納付確認が電子化されています。納付確認の電子化により、車検時に必要となる車検用納税証明書の提示が省略されるようになりました。
ただし、いくら納付確認がオンライン上で確認できると言っても、自動車検査登録事務所で納税確認ができるまでに最大で1週間ほど時間が必要になります。そのため、前もって準備することをおすすめします。
自動車納税証明書の交付請求について

自動車納税証明書の交付請求書について、交付請求書の方法や交付請求に必要な書類を詳しく解説します。
交付請求の方法
交付請求の方法は、具体的に3つあります。
・引っ越しした場合
・紛失した場合
・現金以外の方法(クレジットカード・PayPayなど)で納税した場合
それぞれの方法を詳しく解説します。
引越しをした場合
4月1日から自動車税の納税期限までに引越しを行っている場合、住所変更する前の自動車税納税証明書を交付請求します。そのため、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合には、運輸支局や軽自動車検査協会にて住所変更の手続きを行いましょう。
紛失した場合
納税証明書を紛失した場合、陸運局もしくは自動車税管理事務所、都道府県の税事務所で再発行の手続きが行えます。納税証明書を再発行する際には、本人もしくは代理人が適切な再発行手続きを行いましょう。
納税証明書の再発行に必要な確認事項を以下にまとめました。
・本人が再発行手続きを行う場合:車検証、印鑑(認印)、身分証明書
・代理人が手続きを行う場合:上記以外に委任状が必要
現金以外の方法(クレジットカード・PayPayなど)で納税した場合

現金以外のクレジットカードやPayPayなどで納税手続きをした場合、整備スタッフに支払い方法を正確に伝えましょう。
ただし、現在は普通自動車や軽自動車に限らず、納付確認がオンライン上で確認できるシステムが採用されています。そのため、クレジットカードやPayPayで納税手続きをした場合、再発行に余計な労力や手間をかける必要はありません。
交付請求に必要な書類
交付請求に必要な書類について、具体的に2つ解説します。
・普通自動車の場合
・軽自動車の場合
普通自動車と軽自動車にわけて、詳しく解説します。
普通自動車の場合
普通自動車において、納税証明書を交付請求する場合に必要な書類を以下にまとめました。
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印鑑
・車検証
郵送での手続きの場合、自動車税納税証明書の請求書をWebサイトからダウンロードしたうえで、必要事項を記入した後、返送用封筒を送付しましょう。
軽自動車の場合
次に、軽自動車の交付請求に必要な書類を以下にまとめました。
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印鑑
・車検証
軽自動車の場合、交付請求は市区町村役場の窓口で行います。市区町村で必要になる書類は、普通自動車と原則同じです。
普通車と同様に、郵送で交付請求の手続きを行う際には、自動車税納税証明書の請求書をWebサイトからダウンロード後、必要事項を記入し返送用封筒を送付してください。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
少しでも損をしたくない方は下記の「無料査定はこちら」から無料査定をしてみてください。
| かんたん30秒! 愛車の高価買取なら【カーセブン】 | |
愛車を高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です! \簡単30秒/ |
車検前に納税証明書を発行する方法

車検前に、納税証明書を発行する方法を3つ解説します。
・県税事務所の自動発行機で発行する
・県税事務所の窓口で発行する
・郵送で申請して発行
それぞれの方法を詳しく解説します。
県税事務所の自動発行機で発行する
自動発行機は、県税事務所に設置されています。自動発行機を使うことで、事務所の窓口が混雑している場合や休みなどで対応していない状況でも、発行できるメリットがあります。
ただし、県税事務所によっては、納税証明書を再発行できる自動発行機を設置していない可能性もあります。以下では、県税事務所で納税証明書を発行する手順をまとめました。
- 自動発行機にて、登録番号と車体番号を入力する
- 車体番号入力後、「自動車税を再発行する」を押す
- 対象の納税証明書が再発行される
納税証明書を再発行するためには、車の登録番号と車体番号が必要です。必要であれば、車検証を一緒に持参することをおすすめします。
ただし、車検満了日が自動車税定期課税分の納期経過後の場合、原則発行はできません。
県税事務所の窓口で発行する
県税事務所の窓口で納税証明書を発行する場合、必要事項の記入と認印、車検証が必要です。必要事項の記入とは、「申請人の住所と氏名、車の登録番号、車体番号、申請する方の印鑑」です。
車体番号を記入する際には、7桁の数字を記入し間違いしないよう注意してください。
郵送で申請して発行
郵送で手続きを進める場合、所有する車の管轄の県税事務所に必要書類を送る必要があります。
まずは、各都道府県の公式サイトから申請書をダウンロードして印刷してください。印刷完了後は、必要事項に「氏名や住所、登録番号、車体番号」などを記入し、認印が必要な箇所に押印を行います。
必要事項への記入が完了した後は、返信用封筒を同封した状態で、切手を貼りポストに投函しましょう。
本人以外でも納税証明書を再発行できる?

本人以外の場合、納税証明書が再発行できるのかを以下にまとめました。
・代理人の場合
・相続者の場合
・法人の場合
それぞれ対象とされる再発行方法について、詳しく解説します。
代理人の場合
代理人が納税証明書を再発行する場合、大前提として「本人の委任もしくは再発行に対する同意を得ている状態がわかる書類を準備する必要」があります。
そのため、本人ではなく、代理人が納税証明書交付請求書に委任状を添付した状態で、県税事務所の窓口にて適切な手続きを行いましょう。
代理人の他にも、納税管理人や破産管理人、清算人なども代理人に該当する方です。これらの場合は、委任状の他にもマイナンバーカードや運転免許証なども合わせて持参しましょう。
相続者の場合
相続者が納税証明書を再発行する場合、納税証明申請書以外にいくつか自分で準備する書類があります。必要になる書類は、相続人の本人確認書類と戸籍謄本、もしくは除籍謄本などです。
戸籍謄本とは、相続人であることを証明するために必要になる書類です。除籍謄本とは、被相続人が亡くなったことを証明するために必要になります。
法人の場合
納税義務者が法人の場合、法人名と従業員の名前が記載されている従業員証や、本人確認資料を用意することで再発行の申請が可能になります。
ただし、所属する法人名とは別の従業員が納税証明書を再発行する際、従業員証の代わりに健康保険証を提示することで再発行できます。
運輸支局から納税情報が提供されるまでの目安

運輸支局から納税情報が提供されるまでの目安期間を下記に記載します。
| 支払い方法 | 目安期間 |
| 自動車税事務所や都道府県税事務所の窓口 | 納付から2営業日 |
| 市町村の窓口 | 2ヶ月 |
| 金融機関や郵便局 | 約2週間 |
| スマートフォン決済 | 約1週間 |
| クレジットカード | 約2週間 |
| ペイジー | 約1週間 |
運輸支局へ納税情報が提供されるまでに、どの方法でも一定日数がかかります。とにかく早く納税情報を提供したい場合は、自動車税事務所や都道府県税事務所の窓口や、スマートフォン決済をおすすめします。
自動車納税証明書に関する注意点

ここからは、自動車納税証明書に関する注意点を2つ解説します。
・クレジットカード払いは発行されない
・自動車納税証明書は必ず領収印を確認する
それぞれの注意点を詳しく解説します。
クレジットカード払いは発行されない
クレジットカード払いで自動車税を納付した場合、自動車税の納税証明書は発行されません。さらに、納税期間も5月31日までと期限があるため注意しましょう。
クレジットカード以外にも、インターネットバンキングやATMで納税手続きを済ませた場合も、納税証明書が紙でもらえません。納税証明書の書類を紙ベースで手元に保管したい方は、税務署の窓口で直接支払いすることをおすすめします。
自動車納税証明書は必ず領収印を確認する
自動車納税証明書は、必ず領収印があるのか確認しましょう。領収印とは、納税請求書の右側に付いている部分のことです。
ただし、自動車税を支払っても領収印が押されていない場合、納税を証明することができません。そのため、納税後は領収印を必ず確認してください。
まとめ

この記事では、車検で納税証明書の提出が必要になるのかや、納税証明書の提出を省略できる方法について解説しました。
納税証明書は自動車税を支払ったことを証明する書類で、様々な場面で必要となります。この記事を参考に、愛車の納税証明書を再確認するようにしましょう。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
少しでも損をしたくない方は下記の「無料査定はこちら」から無料査定をしてみてください。
| かんたん30秒! 愛車の高価買取なら【カーセブン】 | |
愛車を高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です! \簡単30秒/ |
もう乗らない…価値が下がる前が売り時
その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!