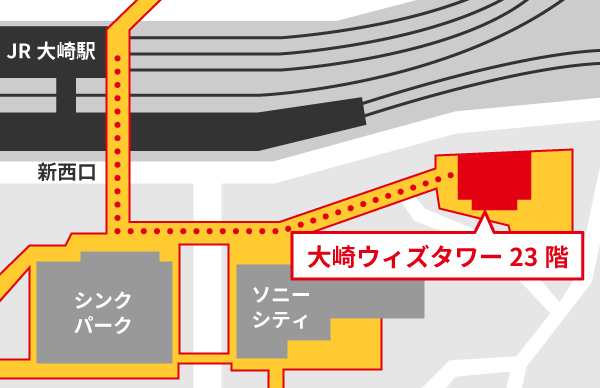「車の売却時に税金はかかる?」「売却した税金は節税することはできる?」と考えている方も多いのではないでしょうか。車を売却する際に節税を行うことは可能です。車の売却額は数百万円になる場合もあるため、税金対策の有無によって手元に残る金額が大きく変動します。
この記事では、個人・法人・個人事業主ごとに車を売却した際にかかる税金について解説します。車売却時の税金で損をしないように、しっかりと知識をつけていきましょう。
一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。税金を引かれた手元に残る金額を少しでも高くして車を売却するなら早めの行動が先決です。
特にカーセブンは大手買取業者で法人・個人事業主にも対応しており、40万円以上も買取相場より高く売れることもあるので、まずは無料で査定価格をチェックしてみてください。
この記事でわかること
- ・車の売却時にかかる税金
- ・車の売却時にできる節税方法
- ・税金対策の注意点
| かんたん30秒! 社用車の高価買取なら【カーセブン】 |
|
社用車をさらに高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です!
\簡単30秒/ |
目次
車の売却で節税はできる?

車を売却する際は、「普通車」の「自動車税」の節税が可能です。
普通車の自動車税は、月割り計算で還付されます。例えば、7月に1.5リッターエンジンを搭載する車を売却した場合、以下の計算により20,300円が還付されます。なお、残月とは、売却した翌月から3月までの月数のことです。
【自動車税還付の計算式】
■年税額÷12ヶ月×残月(100円未満切り捨て)
1.5リッターエンジンの場合
3万500円(年税額)÷12ヶ月×8ヶ月(残月)=20,333円
100円未満切り捨てのため、20,300円還付
このように計算をすることで、還付される自動車税の金額が分かります。なお還付されるのは普通車の自動車税のみであり、軽自動車の軽自動車税は還付対象ではないので、注意してください。
【状況別】車の売却時の節税方法
車売却時の税金事情は、個人・法人・個人事業主でそれぞれ異なります。ここからは、それぞれの立場で車を売却する際にできる節税方法を詳しく紹介するので、事前に確認しておきましょう。
個人の場合
個人で車を売る場合は、普通車の自動車税が売却した時期に応じて月割りで還付されます。ただし、自動車税は4月1日時点で車を所有している人に課せられます。そして、1年分をまとめて支払うため、3月に売却した場合には自動車税が還付されません。そのため、売却時期には注意が必要です。
また、軽自動車の場合は、売却の時期に関わらず自動車税の還付がありません。そのため、軽自動車の場合は、3月に売却した方が出費を抑えられます。
法人の場合
法人の場合は、会社が個人から車を買い取ったときに経費に組み込めます。ただし、その場合には車を会社名義にすることと、事業で使用する目的にすることが必須条件です。
なお、会社が事業用として使っていた車を売却するときは、消費税がかかるので注意しましょう。事業用の車が消費税の課税対象になる理由は、事業者が事業のために使用していた資産の譲渡になるためです。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、購入額よりも売却額の方が低い場合は税金がかかりません。また、売却によって損失が出た場合、税金を減らせる可能性もあります。
一方、売却益が50万円を超える場合は、譲渡所得として課税の対象となります。購入金額と売却金額を把握しておくことが大切です。
個人事業主の場合に関しては詳しく後述します。
車を売却した際にかかる税金
車を売却した際にかかる税金には以下の4つがあります。
・自動車税
・所得税
・消費税
・自動車重量税
しっかりと節税対策をできるように、それぞれの内容をしっかりと把握していきましょう。
自動車税
自動車税は、4月1日時点の車の所有者が1年分の税金を一括前払いで納めます。そのため、売却予定であっても4月1日時点で車を所有していれば、税金を支払わなければなりません。一方、3月末までに車を売却し名義変更も完了していれば、自動車税はかかりません。
なお、自動車税は排気量と購入時期によって税額が変動します。以下に排気量別の自動車税をまとめたので、参考にしてください。
| 排気量 | 2019年9月までに購入 | 2019年10月以降購入 |
| 軽自動車 | 1万800円 | 1万800円 |
| 排気量1000cc以下 | 2万9500円 | 2万5000円 |
| 排気量1000cc超から1500cc以下 | 3万4500円 | 3万500円 |
| 排気量1500cc超から2000cc以下 | 3万9500円 | 3万6000円 |
| 排気量2000cc超から2500cc以下 | 4万5000円 | 4万3500円 |
| 排気量2500cc超から3000cc以下 | 5万1000円 | 5万0000円 |
| 排気量3000cc超から3500cc以下 | 5万8000円 | 5万7000円 |
| 排気量3500cc超から4000cc以下 | 6万6500円 | 6万5500円 |
| 排気量4000cc超から4500cc以下 | 7万6500円 | 7万5500円 |
| 排気量4500cc超から6000cc以下 | 8万8000円 | 8万7000円 |
| 排気量6000cc超 | 11万1000円 | 11万0000円 |
表のように、自動車税は排気量と購入時期で価格が変動します。最低でも数万円単位で価格が変動するので、自動車の売却時期には注意しましょう。
所得税
所得税は、基本的には支払う必要はありません。しかし、車の売却額が大きくなった場合には、所得として見なされ確定申告と所得税の支払いが必要になる恐れがあります。
車の売却では、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象になるので、15%〜45%の累進課税で計算されます。以下に所得金額と所得税率、控除額をまとめたので、参考にしてください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用元:国税庁HP
消費税
消費税は、事業者が事業として車を売却した時に発生します。一般の個人が生活に通常必要な車を売却した場合は、消費税は発生しません。
個人事業主や法人が事業用の車を売却した際には、購入した人から消費税を預かっている状態です。そのため、個人事業主や法人は、その預かった消費税を納税する必要があります。
自動車重量税
自動車重量税は、車の重量に応じて課される税金です。車両重量500kgごとに区分されており、車検時に前払いするように定められています。
新車購入時は原則3年分の自動車重量税を支払います。初回車検以降は、2年ごとに車検があるので、その都度2年分の支払いが発生することを理解しておきましょう。
車の用途によって売却時に発生する税は異なる
車を売却する際には、車の用途ごとに税金が発生するか否かが分かれます。ここでは、通勤用・レジャー用・業務用の用途ごとの税金事情を確認していきましょう。
通勤用
通勤用の車を売却したときには、原則として税金は発生しません。なぜなら、通勤用の自動車を所得税の課税対象とされない譲渡所得として国が定めているからです。
ただし、高級車やスポーツカーのように、通勤目的として認められにくい車を持っていた場合は、事情が異なります。必要以上の動産として、譲渡益が課税対象になるというのが一般的になっています。
また、個人事業主が通勤のために使っている場合や、法人の経営者が事業用の車を通勤に使っている場合には該当しません。事業用車としての処理をしなければならないため、注意しましょう。
レジャー用
レジャー用として利用している車は、生活を豊かにするための動産と見なされるため、車の売却益(譲渡所得)に対して所得税が課税されます。
譲渡所得は、売却益からその車の入手・売却時にかかった費用と特別控除を差し引き、計算が可能です。計算する際は減価償却費を考慮しなければいけません。個人の場合は特別控除として50万円が認められているので、50万円を差し引いた金額が譲渡所得になります。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+減価償却費+売却時にかかった費用)-50万円
計算式の金額に対してかかる所得税を計算することで、税額が確定される仕組みです。なお車の所有期間が5年以上の場合には、長期総合となり譲渡所得を半額とする措置が取られています。
業務用
個人事業主が事業用に使っている車の場合は、売却によって得られた利益は所得となります。
計算方法は、個人がレジャー目的で利用していたときと同様です。先述した計算式を使用して計算してください。売却価格から購入価格と譲渡費用、特別控除を差し引くことで譲渡所得を求め、総合課税としてほかの所得と合算した上で税額を求めます。
個人事業主の場合には、50万円以下の売却となった場合でも節税になる可能性もあるので、計算をしておくことが重要です。売却所得がマイナスの場合は、ほかの所得と合算することで課税対象額を減らすことができます。
そのため、売却額が大したことないからと計上をしないということがないようにしましょう。
中古車は売却時に税金が発生することもある
中古車売却時には、税金が発生する場合があります。売却益が出た場合と売却損が出た場合とで、税額が変動するのでしっかりと確認をしておきましょう。
売却益が出た場合
先述したように、車が50万円以上で売却できて売却益が出た場合は、税金が発生します。税金は総合課税でほかの所得と合算した所得額にかかるので、大きな売却益が出た場合には、一度税金額を計算しておきましょう。
売却損が出た場合
個人事業主は、車の売却で損が出た場合、譲渡利益の損として計上ができます。下記の計算式で計算をしてマイナスになった場合は、マイナス分を課税対象額に組み込むことができ、節税が可能です。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+減価償却費+売却時にかかった費用)-50万円
個人事業主は、高く売れないなら売却しないのではなく、売却を考えることも節税手段の1つです。
個人事業主なら車の売却時に節税できる
個人事業主が車を売却する際には、以下の2点を行うことで節税が可能です。車の売却で損をしないために、しっかりと把握しておきましょう。
・減価償却費を計上する
・譲渡損失を計上する
減価償却費を計上する
減価償却費とは、資産の価値が経年劣化や使用状況によって減少することを反映した費用のことです。減価償却費は経費として計上ができるため、所得税や住民税を減らすことができます。
減価償却費は、毎年一定額を計算して計上します。売却時に購入価額から減価償却費を差し引いた額と、売却価額の差額を計上することが可能です。
たとえば、購入価額が200万円で、売却時に減価償却費が100万円になっている場合は、残存価額は100万円です。このとき、売却価額が50万円だった場合は、残存価額と売却価額の差額である50万円を減価償却費として計上することができます。
減価償却費を入れるか否かで税金額が大きく変動をするので、忘れずに減価償却費を計上するようにしましょう。
譲渡損失を計上する
譲渡損失とは、資産を売却したときに生じる損失のことです。この損失は、事業所得から差し引けます。
譲渡損失は、売却価額から購入価額や修理費などの取得価額を差し引いたものです。たとえば、購入価額が200万円で、修理費が30万円かかった場合、取得価額は230万円になります。このような際、売却価額が100万円であれば、譲渡損失は130万円です。
車の売買費用は金額が大きくなるので、譲渡損失が発生した場合に計上を行わないと、数百万円単位で損をする可能性があります。車の売却時には、譲渡損失が発生しないかもあわせて確認をしましょう。
自動車の売却で節税対策をするポイント
自動車を売却する際には、以下の3つのポイントを意識することで節税対策が可能です。少しでも税金を抑えられるように、しっかりと確認しましょう。
・自動車重量税を支払う前に売却する
・自動車税を支払う前に売却する
・個人事業主は必ず確定申告をする
自動車重量税を支払う前に売却する
1つ目のポイントは、自動車重量税を支払う前に売却をすることです。自動車重量税は、新車の購入時には3年分、車検時には2年分を一括で前払いするものです。自動車重量税は、廃車する場合以外に還付はありません。
そのため、車検を受けてすぐに売却した場合は、2年分の自動車重量税も払ったことになってしまいます。車を売却する際には、車検を受けてから1〜2年を目安に考えておくと良いでしょう。
自動車税を支払う前に売却する
2つ目のポイントは、自動車税を支払う前に売却することです。自動車を保有している場合は軽自動車・普通自動車を問わず、毎年4月1日に軽自動車税もしくは自動車税が課税されます。売却した場合でも、4月1日に所有者であれば支払い義務が生じるので注意しましょう。
なお、普通自動車は売却する際に3月の年度末までの月割分が売却額に上乗せする形で戻ってくることがあります。その一方、軽自動車には還付制度がなく売却時だけでなく、廃車にした際も還付されることはないことを把握しておきましょう。
個人事業主は必ず確定申告をする
個人事業主が車を売却する場合は、譲渡所得(総合所得)として特別控除が50万円まで認められています。譲渡所得は特別控除を踏まえて以下の計算式で計算をしましょう。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+減価償却費+売却時にかかった費用)-50万円(特別控除)
なお個人事業主の場合は、譲渡所得のプラスマイナスに関わらず、恩恵を受けられます。売却額の大小に関わらず必ず確定申告で車の売却分を計上することをおすすめします。
車の売却で返還される税金
車の売却時に還付される税金として自動車税が挙げられます。ここでは、自動車税が返還される仕組みについて学んでいきましょう。
車の売却で返還されるのは基本的に自動車税のみ
車の売却時に返還されるのは基本的に自動車税のみで、軽自動車に課される軽自動車税は返還対象ではありません。
なお、自動車税は排気量によって課税額が異なるので、各自の自動車に合わせて返還額の計算が必要です。また法律上で車の買取の際は、自動車税返還の義務はありません。あくまで買取先次第です。そのため、返還されるか否かは買取先によって異なります。
車を売却する際は、返還の有無を確認しましょう。
返還される自動車税の計算方法
自動車税は以下の計算式で求めることができます。
年税額 ÷ 12か月✕ 名義変更・抹消の翌月から3月までの月数(100円未満切り捨て)
年税額は車の排気量によって異なるので、以下の表から確認して当てはめて計算してください。
| 排気量 | 2019年9月までに購入 | 2019年10月以降購入 |
| 軽自動車 | 1万800円 | 1万800円 |
| 排気量1000cc以下 | 2万9500円 | 2万5000円 |
| 排気量1000cc超から1500cc以下 | 3万4500円 | 3万500円 |
| 排気量1500cc超から2000cc以下 | 3万9500円 | 3万6000円 |
| 排気量2000cc超から2500cc以下 | 4万5000円 | 4万3500円 |
| 排気量2500cc超から3000cc以下 | 5万1000円 | 5万0000円 |
| 排気量3000cc超から3500cc以下 | 5万8000円 | 5万7000円 |
| 排気量3500cc超から4000cc以下 | 6万6500円 | 6万5500円 |
| 排気量4000cc超から4500cc以下 | 7万6500円 | 7万5500円 |
| 排気量4500cc超から6000cc以下 | 8万8000円 | 8万7000円 |
| 排気量6000cc超 | 11万1000円 | 11万0000円 |
車を売却する際の注意点
車を売却する際には、以下の4つの注意点があります。売却時や売却後にトラブルにならないためにも、しっかりと確認しておきましょう。
・リサイクル預託金の消費税を確認する
・税金未納車は売却できない
・個人売買の場合には税金に関するトラブルになりやすいので注意する
・軽自動車の自動車税は返還されない
それでは、詳しくみていきましょう。
リサイクル預託金の消費税を確認する
1つ目に、リサイクル預託金の消費税の確認が挙げられます。
車のリサイクル料金は、消費税の課税対象外です。なぜなら、リサイクル預託金として、自動車リサイクル促進センターに委託したものとされるからです。
リサイクル料金を支払った際と廃車にする際の税率が変わっている場合には、廃車時点での税率が適用されます。追加料金が発生する可能性もあるため、注意が必要です。
リサイクル時には、税率が変わっているか否かを確認しておきましょう。
税金未納車は売却できない
2つ目に税金未納者は売却ができないことが挙げられます。
自動車税を納税していない場合は、次の所有者に名義変更をすることができません。そのため、売却が不可能であるケースがほとんどです。スムーズに売却手続きを進めるためにも、自動車税をはじめとした税金の滞納をしないようにしましょう。
また自動車税を滞納し続けると、最終的に資産や口座などを差し押さえます。そのような面も踏まえて滞納・未納はせずに納税しましょう。
個人売買の場合には税金に関するトラブルになりやすいので注意する
3つ目に個人売買の場合にはトラブルにならないように注意することが挙げられます。
個人売買の場合は、業者が仲介に入らないため、買い手と売り手の間で売買や税金などの手続きを進める必要があります。そのため、自動車税の負担や自動車重量税の負担などでトラブルになりやすいです。
車の売却の際には、手続きや費用負担を相互に理解したうえで話し合うことが重要です。納付する税金を誰が負担するかを明確にし、トラブルを避けましょう。
軽自動車の自動車税は返還されない
最後に、軽自動車の軽自動車税は返還されないことが挙げられます。
軽自動車の場合は、売却のタイミングに関わらず自動車税の還付がありません。なぜなら、軽自動車税には、月割での計算制度がないからです。そのため、売却のタイミングには注意が必要です。
軽自動車に関しては、税金を考慮するのであれば3月に売却した方が出費を抑えられます。年度末の近くになって軽自動車の売却を検討している方は、早めに手続きを進めましょう。
自動車の購入で節税対策をするポイント
自動車は売却時だけでなく、購入時にも節税対策を行うことが可能です。ここでは、以下の2つのポイントを解説します。
・後付け装備を経費計上
・状況に適した計算法を適用する
後付け装備を経費計上
車は購入費用だけではなく、後付け装備も一部経費計上が可能です。
従業員500名以下の中小企業の場合、30万円未満の購入であれば経費計上ができる少額減価償却資産の特例があります。カーナビなど、後付けできる装備が30万円未満であれば、経費(損金)として計上が可能です。そして合計で年間300万円までは計上ができるので、車の売却を考える際は、活用していきましょう。
状況に適した計算法を適用す
状況に適した計算法を適用することも大切です。自動車の減価償却の計算方法には、定率法と定額法があり、国税庁によりそれぞれの減価償却率が定められています。会社の経理状況に合わせて、どちらを用いるかを自由に決められるので、状況に合ったほうを選ぶことが大切です。
定率法は、初年度の減価償却費が多いので、利益が出ている年の節税を重視したい方におすすめです。一方、毎年平均的に節税したい場合は、一定額の減価償却費を計上できる定額法を適用すると良いでしょう。
節税の目的を明確にして、どちらを選択するか決定するようにしましょう。
まとめ
この記事では、車購入・売却時の税金対策を解説しました。車の購入や売却では、大きな額が動くので、適切な税金対策を行って税負担を減らしていくことが大切です。
節税の方法は車の使用用途や個人か法人化でも異なります。各自が最適な税金対策を行えるように、しっかりと知識を確認しておきましょう。
また、一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。税金を引かれた手元に残る金額を少しでも高くして車を売却するなら早めの行動が先決です。
特にカーセブンは大手買取業者で法人・個人事業主にも対応しており、40万円以上も買取相場より高く売れることもあるので、まずは無料で査定価格をチェックしてみてください。
| かんたん30秒! 社用車の高価買取なら【カーセブン】 |
|
社用車をさらに高額で売却するならカーセブンを選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です!
\簡単30秒/ |
もう乗らない…価値が下がる前が売り時
その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!