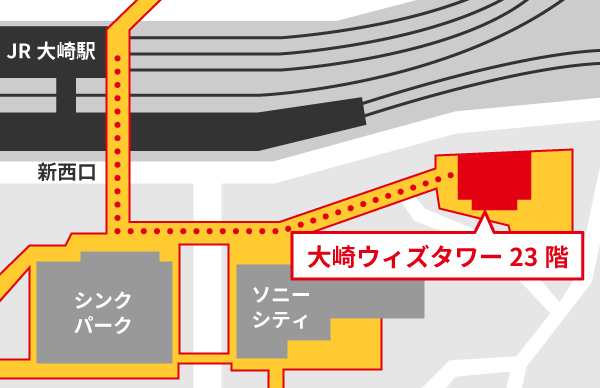ヘッドライトの黄ばみの原因は、ヘッドライトに使用されている「ポリカーボネート樹脂」が変色するためです。ヘッドライトの黄ばみを放置すると、見た目だけでなく視認性が悪くなり、思わぬ事故につながる恐れがあります。また、車検時にはヘッドライトの光量を測定しなければならないため、黄ばみが原因で光量が足りないと車検を通過できません。
本記事では、ヘッドライトの黄ばみの原因と対策を解説します。具体的な対策として使いやすい商品も紹介しているので、ぜひ読み進めてください。
この記事でわかること
- ヘッドライトの黄ばみの原因
- ヘッドライトの黄ばみを除去する方法
- ヘッドライトの黄ばみを予防する方法

黄ばみの原因を知って、美しいヘッドライトにできるように読み進めてください!
目次
ヘッドライトの黄ばみの原因とは?

ヘッドライトが黄ばむ原因は、ヘッドライトに使用されている「ポリカーボネート樹脂」が変色するためです。ポリカーボネート樹脂はガラスよりも強度が高く、衝撃の際に破損した部分が飛散しにくい特性があります。一方で紫外線には弱く、キズがつきやすい性質もあります。
紫外線の影響や細かなキズや汚れによって、ポリカーボネート樹脂が劣化し変色するため、黄ばみが発生するのです。
紫外線などによる劣化
ポリカーボネート樹脂は日光などが当たり続けると、紫外線の影響で劣化して黄ばんでしまいます。ヘッドライトの表面には、日光などから守るためにコーティングが塗装されていますが、洗車や経年により次第に剥がれていきます。塗装が剥がれた部分から紫外線などの影響でヘッドライトの劣化が進行してしまうのです。
また、ポリカーボネート樹脂は熱にも弱いため、ヘッドライトにハロゲンランプを使用していると、ランプが発する熱によって内部から劣化するケースもあります。
細かなキズや汚れ
走行時の飛び石などでヘッドライトに細かいキズがつくと汚れもつきやすくなります。小さなキズでも何度も同じ場所にダメージが蓄積していくと、キズが次第に深くなっていきます。深くなったキズには汚れが入り込みやすくなるため、ヘッドライトのにごりや黄ばみの範囲が増えていくのです。
ヘッドライトは車両の前方にあるため、キズがつくのを避けるのは難しいでしょう。ヘッドライトの黄ばみを放置してしまうと、夜間の走行時などに光量が足りず、視界が悪くなってしまう可能性もあります。そのため、黄ばみが起きてしまう前に日常的にメンテナンスしておく必要があります。

ヘッドライトが黄ばんでいるだけで見た目の美しさが損なわれるだけでなく、夜間の走行時に必要な明るさも奪われてしまいます。すでに黄ばんでしまった人は除去する方法があるので、次の章を読み進めてください!
ヘッドライトの黄ばみを除去する方法

ヘッドライトの黄ばみを除去する方法は、自力で施工するかプロに依頼するかのどちらかです。黄ばみの度合いによって対策が異なるので、ヘッドライトの状況に合わせた方法で除去しましょう。いずれにしても自分で施工する自信がない方は、プロに任せるのがおすすめです。
市販のヘッドライトクリーナーを使う
軽い黄ばみなら市販のヘッドライトクリーナーで落とせる可能性が高いです。黄ばみが発生していなくても日頃から手入れをしておくことで、黄ばみがない状態をキープできます。以下のステップで、手入れの手順を簡単に紹介します。
【ステップ】
マスキングテープなどをボディに貼って養生すれば、ボディにキズがつくのを未然に防げます。
クリーナーには研磨剤とコーティング剤がセットになった便利なものがあるため、手入れに手間をかけたくない方はセットになっている商品を購入してください。

ヘッドライトクリーナーの参考商品:シュアラスター ゼロリバイブ
耐水ペーパーやコンパウンドで磨く
ヘッドライトクリーナーで黄ばみを落とせない場合は、耐水ペーパーやコンパウンドで磨く方法を試してみてください。ヘッドライトの黄ばみやくすみを除去するには、施工するための道具や材料が必要です。ここでは、本格的に施工する場合に必要なアイテムと施工手順を紹介します。
・ヘッドライトクリーナー
・耐水ペーパー(研磨ペーパー)
・コンパウンド(液状の研磨剤)
・マスキングテープ
・マイクロファイバークロス
・コーティング剤塗布用のスポンジ
・コーティング剤
【ステップ】
黄ばみが落ちない場合は、耐水ペーパーを水でぬらしながら全体を磨く

用意するのもが多く、面倒だと感じる方にはすべてセットになった商品がおすすめです。下の商品も参考にしてください!

ヘッドライトクリーナーの参考商品:CCI 車用 ヘッドライトコート剤 スマートシャイン ヘッドライトコートNEO
プロに依頼する
カー用品店やガソリンスタンドなどでヘッドライト磨きやコーティングを依頼できます。上の2つの手順を読んでみて自分で行うのは難しそう、時間がかかって大変そうと思った方はプロにお任せしましょう。
紹介した2つの手法で使う商品は高くても2,000円程度で購入できますが、プロに依頼すると3,000〜5,000円の費用がかかります。その代わり、仕上がりの信頼性は高いといえます。
ただし、黄ばみの状況によってはヘッドライト自体を交換しなければならない場合もあります。その場合の費用は整備工場により異なりますので、別途見積もりを取るようにしてください。
ヘッドライトの黄ばみを予防する方法

ヘッドライトの黄ばみを予防するためには、日常の手入れをするほかに、紫外線を遮断する次の方法が有効です。
コーティングや黄ばみ防止フィルムを施工する
ヘッドライト用のコーティングや黄ばみ防止フィルムが市販されているので、購入して施工しましょう。それらの商品を使用すると紫外線からヘッドライトを守る効果が期待できます。紫外線を遮断できれば黄ばみの発生を抑えられ、きれいな状態をキープすることが可能です。
商品によって施工後の効果の持続期間は異なります。数か月~2年程度と幅があるので、施工性や効果の持続性などを考慮して購入するようにしてください。なお、専門店にコーティングを依頼して施工すると、3~5年ほど効果を維持できる場合もあります。

黄ばみ防止フィルムの参考商品:ホルツ ヘッドライトコーティングシート
車体カバーなどで紫外線を避ける
車に日光が当たらないように車体カバーをかければ、ヘッドライトの黄ばみを予防できます。日頃利用する駐車場では日光を避けられない場合、日中はヘッドライトを含む車体全体に日光が常に当たる状態になります。
そこで、車を使わないときは車体カバーをかけておけば、直射日光を防げるようになるでしょう。ヘッドライトの劣化はもちろん、車体全体を保護できるため、愛車を長持ちさせたい方はこまめに車体カバーをかけるようにしてください。

車のサイズによって車体カバーの大きさは異なりますので、持っていない方は自分の車にあわせて車体カバーの購入を検討しましょう!
ヘッドライトの黄ばみを放置するとどうなる?

ヘッドライトの黄ばみを放置すると、見た目が悪くなるだけでなく、周囲を明るく照らせなくなってしまいます。ヘッドライトの光が暗くなってしまうと、トンネルや夜間の走行時に視認性が悪くなり、思わぬ事故につながるおそれもあります。
また、車検時にはヘッドライトの光量を測定しなければならないため、光量が足りないと車検を通過できません。その場合、ヘッドライトを交換しなければならない可能性があるため、想定していたよりも車検時の出費が多くなることがあります。

ヘッドライトをきれいな状態にしておけば、黄ばみは未然に防げます!日頃のこまめなメンテナンスが効果的ですよ!
よくある質問
ヘッドライトが黄ばむ原因は、ヘッドライトに使用されている「ポリカーボネート樹脂」が変色するためです。ポリカーボネート樹脂はガラスよりも強度が高く、衝撃の際に破損した部分が飛散しにくい特性があります。一方で紫外線には弱く、キズがつきやすい性質もあります。
紫外線の影響や細かなキズや汚れによってポリカーボネート樹脂が変色するため、黄ばみが発生するのです。
あります。ヘッドライトの黄ばみを除去する方法は、自力で商品を購入して施工するか、プロに依頼するかのどちらかです。黄ばみの度合いによって対策が異なるので、ヘッドライトの状況に合わせた方法で除去しましょう。
落とせません。黄ばみの原因となる汚れを重曹や洗剤で落とすことは可能です。ただし、ポリカーボネート樹脂はアルカリ性に弱いため劣化を促進させる恐れがあります。
メラミンスポンジのメラミン樹脂という素材は硬度が高く、ヘッドライトの表面を削ってしまうためおすすめできません。耐水ペーパーのような役割をはたせる可能性はありますが、表面が細かなキズでくもりが発生してしまう場合があります。
そのため、コンパウンドなどの粒子の細かい研磨剤による仕上げが必要です。表面を削るなら番手が明確な研磨ペーパーを使うほうが仕上がりの調整がしやすいでしょう。
もう乗らない…価値が下がる前が売り時
その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!
WEBからのお申し込み
審査だけでもOK!
お電話からのお申し込み
営業時間8:30~20:00