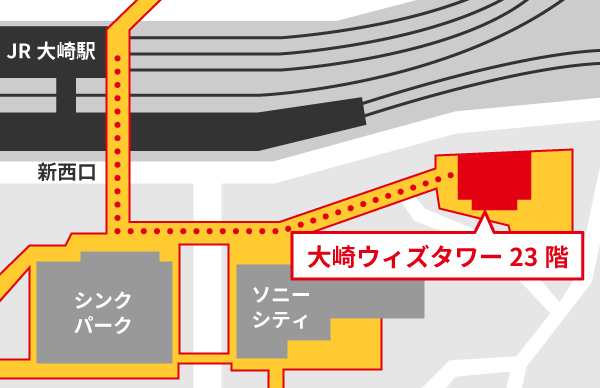小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則や道路交通法で定められている自動車の一種です。
農耕トラクタや農業用薬剤散布車などの農耕作業用、シャベル・ローダやグレーダといった荷役運搬・土木建設作業用の自動車のうち、条件を満たしたものが「小型特殊自動車」にあたります。
小型特殊自動車の規定を知らずに公道を運転していると法律違反になってしまう可能性があるため、注意事項を確認したうえで運転しましょう。
この記事でわかること
- ・小型特殊自動車の種類
- ・小型特殊自動車免許の取得方法
- ・小型特殊自動車を利用するときの注意点
| 契約後の減額は一切なし! 安心して車を売却するなら【カーセブン】 |
|
できるだけ高く査定してもらうなら、買取を選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です!査定金額に納得し、買取契約に至る場合は、当日内に一部の契約金が前払いにも対応しています。 \簡単30秒/ |
目次
小型特殊自動車とは

小型特殊自動車とは、道路運送車両法や道路交通法で定められている自動車の種別のひとつです。
乗車定員は1名(運転席以外に座席がある場合は2名)で、農作業や工事現場などの環境で活躍します。

大型特殊自動車と車の種類はほとんど同じですが、最高速度や車両の長さ、車両の高さなどによって区別されます。
小型特殊自動車の種類
小型特殊自動車は「農耕作業用」と「荷役運搬・土木建設作業用」の2つに分類されます。
| 分類 | 自動車の種類 | 基準値 |
| 農耕作業用 | ・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・刈取脱穀作業用、田植機及び 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度が35km/h未満 |
| 荷役運搬・ 土木建設作業用 |
・ショベル・ローダ ・タイヤ・ローラ ・ロード・ローラ ・グレーダ ・ロード・スタビライザ ・スクレーパ ・ロータリ除雪自動車 ・アスファルト・フィニッシャ ・タイヤ・ドーザ ・モータ・スイーパ ・ダンパ ・ホイール・ハンマ ・ホイール・ブレーカ ・フォーク・リスト ・フォーク・ローダ ・ホイール・クレーン ・ストラドル・キャリヤ ・ターレット式構内運搬自動車 ・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 ・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを 有する自動車及び国土交通大臣の指定する 特殊な構造を有する自動車(林内作業車、 原野作業車、ホイール・キャリア、草刈 作業車等) |
・車両の長さが4.7m以下 ・車両の幅が1.7m以下 ・車両の高さが2.8m以下 (ヘッドガード等を除いた 高さは2.0m以下) ・最高速度が15km/h以下 |
小型特殊自動車と新小型特殊自動車の違い
新小型特殊自動車という名称自体は、法律上で明確に定義されているものではありません(2024年12月時点)。
道路交通法と道路運送車両法施行規則の2つの法律での車の種別の違いから、新小型特殊自動車と分類されるものが出てきました。
道路交通法の小型特殊自動車には該当せず、道路運送車両法施行規則では小型特殊自動車に該当するものを「新小型特殊自動車」と呼ぶことがあります。
2つの法律では車両の長さや車幅は同じですが、車両の高さに違いがあります。
| 道路交通法 | 2.0m以下(※) |
| 道路運送車両法施行規則 | 2.8m以下 |
※ヘッドガード等がついている場合は、ヘッドガードを除いた部分が2.0m以下。ヘッドガードを含めたときの高さが2.8m以下。

新小型特殊自動車で公道を走行する場合は、大型特殊自動車免許(「農耕用に限る」を含む)が必要です。
小型特殊自動車の免許の取得方法
小型特殊自動車は普通自動車免許があれば運転できるため、普通自動車免許を所有している方は新たに取得する必要はありません。

これから小型特殊自動車免許を取得したい場合は、取得条件や必要な書類を確認したうえで、取得の手順を踏みましょう。
小型特殊自動車の免許の取得条件
小型特殊自動車免許を受験するためには、いくつかの条件が設けられています。
たとえば、東京都の場合は以下の条件です。
・16歳以上
・住所が東京都内
・視力が両眼で0.5以上(一眼が見えない方は、もう一方の眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上である)
ただし、過去に免許の取消処分等(初心取消以外)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講していることに加え、欠格期間(免許の再取得ができない期間)が経過したあとでなければ受験できません。
小型特殊自動車の免許取得に必要な書類
取得条件を満たしている方は、必要な書類を用意しましょう。
免許の取得状況や外国籍であるかどうかなどによって必要な書類が異なります。
初めて免許を取得する方 >
住民基本台帳法の適用を受けない方 >
すでに何らかの運転免許証を持っている方 >
たとえば、警視庁が管轄する東京都での必要書類は以下のものです。
初めて免許を取得する方
| 書類 | 詳細・例 |
| 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し | マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの |
| 本人確認書類 (住民票の写し以外) |
・健康保険証 ・マイナンバーカード(通知カード不可) ・住民基本台帳カード ・旅券(パスポート) ・在留カード ・特別永住者証明書など |
| 申請用写真 | 縦3cm×横2.4cm(1枚) 無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの |
上記の書類に加えて、WEB予約時に受け取ったQRコードまたは受付番号が必要です。
住民基本台帳法の適用を受けない方
住民基本台帳法の適用を受けない方とは、以下のいずれかに当てはまる方です。
・3か月以下の在留資格が決定した
・短期滞在の在留資格が決定した
・外交または公用の在留資格が決定した
・その他、法務省令で定めるものに該当しない
| 書類 | 詳細・例 |
| 旅券等 | ・旅券 ・外務省の発行する身分証明書 ・権限のある機関が発行する身分を証明する書類 |
| 旅券等以外の本人確認書類 | ・健康保険証 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・官公庁が法令の規定により交付した免許証 ・許可証 ・資格証明書等の書類 ・学生証 ・社員証等身分を証明するに足りるもの など |
| 免許申請上の住所に関し、 居住地に滞在していることを証明する書類 |
|
| 申請用写真 | 縦3cm×横2.4cm(1枚) 無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの |
上記の書類以外に、WEB予約時に受け取ったQRコードまたは受付番号も必要です。
すでに何らかの運転免許証を持っている方
すでに何らかの運転免許を持っている場合は、以下の3つの書類のみで申請できます。
・運転免許証
・申請用写真
縦3cm×横2.4cm(1枚)
無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
・予約完了時のQRコードまたは受付番号
小型特殊自動車の免許を取得する流れ
必要な書類を揃えられたら、免許センターや運転免許試験場で手続きを行います。
申請をして、適性検査(視力検査など)と学科試験を受けたあとに合格であれば小型特殊自動車免許が交付されます。

最短1日で取得可能なので、「すぐに必要」という方でも安心です。
小型特殊自動車の免許取得にかかる費用
小型特殊自動車免許の取得にかかる費用は以下の2つです。
- 受験料
- 免許証交付料
たとえば、東京都の場合、受験料1,500円と免許証交付料2,050円がかかり、3,550円を支払う必要があります。
小型特殊自動車を利用するうえでの注意点
小型特殊自動車を利用する際には、以下の3つのことに注意しましょう。
軽自動車税(種別割)が課税される
公道を走るかどうかに関わらず、小型特殊自動車を所有していれば自動車税がかかります。
たとえば、有田川町や板橋区では以下のようになっています。
| 農耕用 | 年間2,400円 |
| 荷役運搬・土木建設作業用 (フォークリフトなど) |
年間5,900円 |
また、小型特殊自動車を所有するためには、登録申請とナンバープレートの交付が必要です。
以下の書類を持って、居住している地域の運輸支局や検査登録事務所で申請しましょう。
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
・販売証明書(販売店で購入した方)、譲渡証明書(他人から譲り受けた方)
・所有している車両の車名、型式や車台番号のわかる書類
保安基準を満たさないと公道を走行できない
トラクタなどをはじめとする一部の小型特殊自動車は、保安基準を満たすことで公道も走行できるようになります。
直装式と被けん引式の2つのタイプで保安基準が異なる部分もあり、以下のようなものが定められています。
| 直装式 | ・バックミラーを装備している ・かじ取車輪にかかる荷重が車両総重量の20%以上になっている ・ヘッドランプやテールランプなどの灯火器類がほかの走行車から確認できる ・安定性の基準を満たしている など |
| 被けん引式 | ・農耕トラクタとけん引式農作業機をセーフティーチェーンなどの丈夫な設備でつないでいる ・ランプや反射器などが適切な場所についている ・バックミラーを装備している ・かじ取車輪にかかる荷重が車両総重量の20%以上になっている ・安定性の基準を満たしている など |
小型特殊自動車によっては保安基準が異なる場合があるため、説明書などで確認のうえ使用する必要があります。

保安基準を満たしていない場合は公道を走行できないため、満たしているかどうか確認してから運転しましょう。
個人間で譲り受けた場合は名義変更が必要になる
個人間での譲り受けの場合であっても名義変更が必要です。
必要な書類を持って、居住地の役所の税務課で申請しましょう。

申請を行わないと譲った方に税金の支払いが求められる可能性もあるため注意が必要です。
譲り受け方によって提出する書類は異なります。
| 他人から譲り受けたとき | ・軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・廃車申告受付書(廃車証明書) ・譲渡証明書・朱肉を使用する認印(法人の場合は代表者印) ・窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など) |
| 他人への譲渡や 廃棄するとき(※1) |
・軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・朱肉を使用する認印(法人の場合は代表者印) ・窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など) |
| 所有者の方が亡くなられたとき | ・軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート(※2) ・新しく所有者となる方の朱肉を使う認印 ・亡くなられた方との関係性がわかる書類(※3) ・窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など) |
※1 代理人(所有者と同世帯の者を除く)による申請の場合は、所有者の委任状が必要です
※2 新しく所有者となる方が亡くなられた方と同世帯かつ、同一ナンバーを希望する場合は不要です
※3 遺産分割協議書などの相続が確認できる書類や、家族関係がわかる書類など
名義変更の手続きを行うのが面倒だと感じた場合は、代行の依頼もできます。
また、中古車の買取店に依頼すれば名義変更をしてもらえる可能性もあるため、名義変更を代行してもらえる買取店での売却もおすすめです。
中古車を安全に購入・売却するならカーセブンに相談!
乗り換え・買い替えを考えている場合は、無料査定で愛車の価値を確認してみるのがおすすめです。
カーセブンでは車の買取と販売を行っています。今の車を売却して、売却金を受け取ることで、新しい車の購入費用に充てられます。
「契約後の減額なし」「7日間キャンセル可能(キャンセル料なし)」「当日中に前払い可能」といった点に加えて、無料査定だけでも可能な点は、お客様に大きく評価されています。

車の買取に関して不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください!
よくある質問
小型特殊自動車免許をはじめ、大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許、大型二輪免許、普通二輪免許を所有していれば運転できます。
小型特殊自動車は、大きく分けて「農耕作業用」と「荷役運搬・土木建設作業用」の2つがあります。詳しくはこちらで解説しています。
できません。原付を運転したい場合は、原付免許を取得するか、大型自動車免許や中型自動車免許、普通自動車免許などの原付も運転できる免許を取得する必要があります。
運転できます。
必要な費用は、受験料と免許証交付料の2つです。たとえば、東京都の場合、受験料1,500円と免許証交付料2,050円の合計3,550円が必要です。
車のご売却、安心で選ぶなら カーセブン
もう乗らない…価値が下がる前が売り時
その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!
WEBからのお申し込み
審査だけでもOK!
お電話からのお申し込み
営業時間8:30~20:00